皆さんこんにちは!営業部のHです♪
10月に入り、朝晩がぐっと冷え込むようになってきましたね…
患者さんとの会話の中でも、「風邪ひきそう」「のどが乾く」なんて言葉が増えてきたのではないでしょうか?
気温の変化に加えて、空気の乾燥で唾液分泌が減りやすくなるこの季節。
実は“口腔内”も、う蝕が進みやすくなる時期なんです。
日々のブラッシングに加え、フッ化物(以下「フッ素」)によるケアを取り入れることで、う蝕になりにくい口腔環境を維持しませんか?
フッ素には、う蝕の発生と進行を抑える3つの大きな働きがあります。
1. 再石灰化の促進
食事や間食をするたびに、歯の表面では脱灰と再石灰化がくり返されています。脱灰によって溶け出したカルシウムやリンを再び取り戻す働きを助けるのがフッ素です。フッ素イオンが歯面に存在することで、ミネラルが効率よく沈着し、初期う蝕の修復につながります。
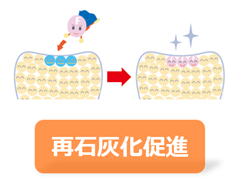
2. 抗菌作用
フッ素はう蝕原因菌(ミュータンス菌など)の代謝を抑制し、酸をつくる働きを弱めます。酸が減れば、歯の表面が溶けにくくなり、う蝕の進行を防ぐことができます。

3. 歯質強化
フッ素が取り込まれたエナメル質は「フルオロアパタイト」という構造を形成し、通常のハイドロキシアパタイトより酸に溶けにくくなります。つまり、フッ素は“酸に強い歯”をつくるサポートをしているのです。

これら3つの作用が組み合わさることで、フッ素は「う蝕になりにくい口腔環境」をつくり出しています。
フッ素の基礎知識については、こちらのコラムで詳しく紹介していますので、ぜひチェックしてください♪
う蝕予防に活用したいフッ素ですが、濃度や使用場面に応じたいくつかの活用方法があります。
1. フッ化物配合歯磨剤
ご自宅での毎日のセルフケアに使用するフッ素ケア。
毎日のブラッシング習慣に組み込むことで、持続的な効果が得られます。
2. フッ化物洗口剤
液体状のため、歯間部や矯正装置の周囲などハブラシの毛先が届きにくいところにも行きわたりやすく、ぶくぶくうがいだけと手技も簡便なため、学校や職場などでの集団使用にも適しています。使用後に水でゆすぐ必要がないため、フッ素がより口腔内に留まります。
3. フッ化物歯面塗布剤
歯科医院で行うプロフェッショナルケア。最も高濃度ですが、定期的に継続して受ける必要があります。
この3つを組み合わせて、セルフケアとプロケアの両面からう蝕予防を行うのが理想的です。
この中でも今日は、フッ化物歯面塗布剤についてみていきましょう♪
歯科医院で使われるフッ化物歯面塗布剤には、ジェル・液体・フォーム(泡状)の3タイプがあります。
それぞれに特徴とメリット・デメリットがあり、対象や施術環境に応じて使い分けることが大切です。
1. ジェルタイプ
〈メリット〉
・粘性が高いため、歯面にとどまりやすい
・塗布中の視認性が良い
〈デメリット〉
・塗布後、薬剤をふき取る必要がある
・粘性が高いため、歯間部や補綴装置周囲には行きわたりにくいことも
2. 液体タイプ
〈メリット〉
・液体のため、歯間部や補綴装置周囲にも広く行きわたる
・塗布後、薬剤をふき取る必要がない
〈デメリット〉
・塗布した箇所が分かりづらい
3. フォームタイプ
〈メリット〉
・きめ細かい泡が歯間部や隣接面にも行きわたる
・吐出のみで余剰のフッ化物を除去しやすい
・トレー法にも使用しやすい
・流れ落ちにくく操作性が高い

〈デメリット〉
・補綴装置が入っている箇所など、該当部位のみを避けて塗布するのが難しい
フッ化物歯面塗布剤には、酸性タイプと中性タイプがあります。
どちらも9000ppmの高濃度フッ化物を含みますが、pHの違いによって特性が異なります。
ここでは「用法」「市場状況」「適応」に絞って整理します。
①用法
酸性タイプは年1〜2回の単回塗布が基本とされています。
一方、中性タイプは2週間に3〜4回の塗布を1クールとし、年間1〜2回実施とされています。
②市場状況
現在市場に出ている歯面塗布剤の多くは酸性タイプです。
中性タイプは商品数が少ないものの、補綴装置や矯正患者さんへの応用など、多様な場面での活用が期待できますね。
③適応
酸性タイプは、補綴装置などがない歯列全般や集団塗布に適しています。
一方で、チタン合金に腐食作用、ポーセレンに劣化作用があるという報告があるため、対象の選定が必要です。
中性タイプは、ブリッジや補綴装置が入っている患者さん、矯正治療中の患者さんにも安全に使用できるのが特徴です。

フッ素の働きは「再石灰化の促進」「抗菌作用」「歯質強化」の3本柱。
プロフェッショナルケアには欠かせないフッ化物歯面塗布剤ですが、さまざまな剤型・濃度のものがあります。
これからの季節、乾燥や唾液量の低下でう蝕リスクが上がる今こそ、
「どのようなフッ化物歯面塗布剤を、誰に、どのように使うか」を意識してみませんか?
これを機に、改めてフッ素の役割を理解し、個々に合わせたケア提案ができるようにしていきたいですね。
フッ素の基本的な働きや、日常のケアでの取り入れ方については、過去のコラムでも詳しく紹介しています。
臨床現場での活用に役立つ内容もございますので、ぜひこちらもご覧ください!
フッ化物の応用方法について | 歯科衛生士コラム | お役立ち情報 | クラブサンスタープロ
フッ素の基礎知識 | 歯科衛生士コラム | お役立ち情報 | クラブサンスタープロ
意外と知らない?海外でのフッ化物応用 | 歯科衛生士コラム | お役立ち情報 | クラブサンスタープロ
それでは、次回のコラムもお楽しみに!!